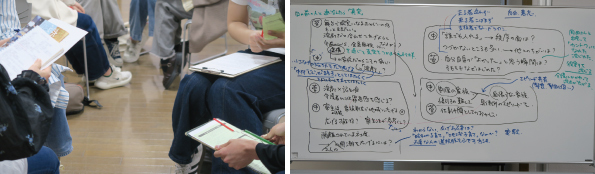【 ユースプログラム2025「新しい演劇鑑賞教室」(前期)①レポ―ト】
演劇作品の鑑賞と参加者同士の対話などを組み合わせたユースプログラム2025「新しい演劇鑑賞教室」前期が5/24(土)にスタートしました。
■演劇ワークショップ「老いを演じてみよう」
企画監修の長津結一郎さん進行のもと、ワークショップ講師「恋はみずいろ」の作・演出であり介護福祉士の菅原直樹さんが登場。菅原さんは演劇活動の傍ら介護の仕事に携わる中で「演劇と介護は相性がいい」と感じたそう。「私自身がお年寄りと触れ合ううちに前向きになれた。今日は私が介護の世界で観た、老いの豊かな世界を体験してもらいたい」と挨拶。早速、介護現場で行う遊びのリハビリテーション「遊びリテーション」が始まりました。

今回は学生・社会人を含む19名が参加。まず、体の部位に1~6まで番号を振り指名された「将軍」の言う数字に従って、全員が該当する部位を指さすルール。数字が複数になったり他者の身体を指すようになったり、徐々に難易度が上がっていくとバランスを崩してフラつく参加者も。「社会(学校や職場)において"できない人"はできるまで努力を強いられる。でも"遊び"はできなくてもいい。できない人がいるから人間味があって面白い」と菅原さん。
続いて「椅子取り鬼」。全員で協力し、鬼役の菅原さんを空いている椅子に座らせないよう阻止するゲームです。開始直後は様子を見ながらクリア。その後、話し合う時間を設けて作戦を立てるも、あえなく失敗し、みんなで失笑。菅原さんは「コミュニケーションは言葉に頼りがち。演劇の原点は、子どものころにやった身体を使った遊びにある」と語りました。
次は「Yes,andゲーム(介護バージョン)」。一人が介護職員役になり「〇〇の時間ですよ」と声をかける。認知症の人役は文脈のずれた返答をするが、介護職員は「いいですね」と肯定するゲーム。「ご飯の時間ですよ」に対して「ドーナツになりたい!」と返答があり「いいですね、今度身体に小麦粉を塗ってみましょう」といった具合。予想外のやり取りに周囲も盛り上がります。「若い人はゲーム感覚で楽しそうですが、介護現場、特に認知症患者の家族にとっては難しいと感じる人が多い。自分が普段からいかに否定のコミュニケーションをしているか気づきがあったのでは」と菅原さん。
今度はそこに"認知症の人の発言を否定して現実に引き戻そうとする介護職員"が加わります。食堂へ行くよう促す職員に対し「きゃりーちゃんがここにいるから行きたくない!」と認知症の人役。「そんな人はいないから食堂に行きましょう」「いや、行きたくない!」とだんだん声を荒げる二人。するとベテラン介護士役が登場し、「今日はきゃりーちゃんのコラボメニュー。まだ誰も食べてないから一緒に行こう」と答えると「素敵!行きたい」と快諾。相手を否定せず食堂に誘導する姿に自然と拍手が起きました。

「頭ごなしに否定されると自分自身を否定されるような気分になった」と語る認知症の人役。菅原さんは「介護する側に精神的な余裕がなくなってしまうと、コミュニケーション不全となる。価値観の押し付けがどういう状況になるのか疑似体験してもらった。認知症の方と関わるときは、自分が見ている世界が絶対ではなく、相手にしかわからない世界があるということを理解してください」と話して前半が終了。
休憩をはさんで後半は、5人で雑談するシーン。一人の認知症の人役を全員で否定するパターンと肯定する2パターンを演じました。認知症の人役は、ある台本に書かれたセリフしか話せません。まず、4人が完全に無視する否定パターンから。「宝くじが当たったらどうする?」というテーマに旅行の話で盛り上がる中、側に居ながら会話に加われない認知症役。「わしは行かん」という投げやりな台詞で幕を閉じました。
続いて、認知症の人役が何を言っても4人が全て受け入れる肯定パターン。すると今度は和やかな雰囲気で会話が終了。認知症の人役は「無視されると寂しくて荒々しいセリフを選んでしまうし、この状態が続くと何も話さなくなるかも。肯定は受け入れられた感じがして優しいセリフを選んだ」と周囲の対応による心境の変化を語りました。

菅原さんは、「介護現場では不適切な対応をすることで、高齢者の攻撃的言動や介護への抵抗態度として現れることがある。でも、相手に寄り添ったアプローチで改善できることもある」と話し、「認知症を知って、これほど恐ろしい病があるのかと思ったが、関わり方次第で共に楽しむこともできる。僕が歳を取って認知症になっても、身体を使った遊びや人と触れ合うのは楽しいと思う。記憶に残る景色は美しいけど、いまこの瞬間に広がっている景色も豊かなもの。超高齢化社会になって介護はみなさんにも身近な問題。孫には孫としての関わり方があると思うので模索してください。その時は今を楽しむ生活をしてください」とワークショップを締めくくりました。
■プレレクチャー「劇場で考える~これからの家族~」
一般参加者も加わったプレレクチャーには40名が参加。まずは4~5人のグループに分かれ、参加したきっかけやテーマである「これからの家族」について自身の考えを話します。
講師の菅原さんが「劇団OiBokkeShi(おい・ぼっけ・し)の由来は、老いと呆けと死。どの言葉にもマイナスのイメージがあると思いますが、介護職員として働いて、老いの豊かな世界を演劇などの芸術文化を通じて地域に発信できればと思って活動しています」と自己紹介。「老人ホームでゆっくり歩くおばあさんの姿に人生がにじみ出ていて、役者として負けたと衝撃を受けた。戦前戦後の激動の時代を生き抜いてきた高齢者たち。人生のストーリーを字幕で流すだけで立派な演劇になると思った」と振り返ります。

11年前に地元のワークショップで岡田忠雄(99歳)さんと出会ったことをきっかけに劇団を立ち上げたこと。"おかじい"の愛称で看板俳優になった岡田さんを主人公にした作品のこと。「"おかじい"は生活面ではできないことが増えたが、演劇という虚構の世界では出来ることが増えている」と語ります。
『恋はみずいろ』には、高齢者のほかにコミュニケーションに苦手意識のある若者や、脳血管障害の後遺症のある人とその妻が出演。「介護する側、される側がともに演じてその瞬間を共有する。社会生活では我慢することが多いけど、稽古場ではそれぞれを尊重して演技している。現実ではうまくいかなくても虚構の世界で自分らしさを発揮できれば、生活する上での自信になるのでは」と菅原さん。「作品では、自分の知らなかった親の一面を介護を通じて他者から知らされ、家族の境界が曖昧になる。家族というものの関係性をどう編み直していくかを描いています。"おかじい"の芝居に惹かれて集まったネットワークが作品をも支えている」と思いを語りました。
続いて中村路子さんが登場し、久留米市内の子育て拠点『じじっか』の活動について報告しました。子どもが1歳と3歳の時に離婚し、ひとり親当事者の経験をもとに市民活動団体を設立。「ママを一人にしない」を目標に3組の母子家庭の支援をスタート。現在は320世帯まで増え、単身者から高齢者までたくさんの世代が集まって「血縁のない大家族づくり」をテーマに活動を行っています。
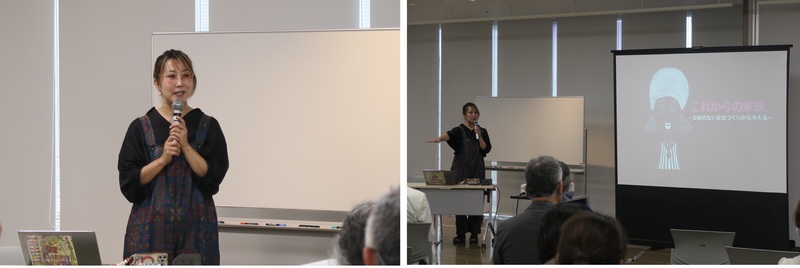
合言葉は「ラッキーループを巻き起こせ!」。今では「100人の貧困世帯の脱出」と「地域子育て」の2つを目標に掲げ、親子食堂で週5回食事を無料提供しています。無料塾を開催したり、子どもたちが自分の努力でほしいものを獲得する仕組みなどもつくり、「当事者として社会に足りないと思ったこと、ニーズに適していないサービスを自分たちのサイズでカタチにしてきた」と中村さん。心に余裕がないと反発心として現れて悪循環となる。各自が家で頑張っていることを"分ける"ことで負担を軽減し、余裕を生み出す仕組みを子どもたちも交えて作ってきました。
ここで、『じじっか』で過ごしている高校生4人が登場。中村さんの「血縁がなくても家族になれると思いますか?」の問いに、それぞれが答えました。「自分のことを信じてもらいたい人たち。血がつながっていなくても、いつの間にか自然と家族になれると思います」「親と同じ立場で相談を聴いてくれる」「家族以外で自分を受け入れてくれる場所が『じじっか』」「信じられる大人、話せる同級生、ちょっと年上の先輩がいて、落ち着ける場所」と語り、答えは全員"イエス"。
最後に中村さんがスライドで「サンタの荷物」を紹介。「人は空っぽの袋をもって生まれて来る。人生の中で後悔やトラウマ、悲しみなどの想いが袋につまり、抱えきれないほど重くなっていく。たとえ150キロの重さがあっても、それを1キロずつに分けて解決することで、一人の重荷を軽くすることが出来る」と語りました。

進行の長津さんがゲストの二人に「これからの家族」について一言ずつコメントを求めると、中村さんは「家族というテーマを毎日意識して活動している。血縁にとらわれない家族=無条件で愛を持てるか、だと思います」と語り、菅原さんは「芸術文化を鑑賞するだけでなく、演劇を通じて老いや介護家族の問題を疑似体験してもらい、大切な人との向き合い方、他人とのつながりを考えてもらえたら」と答え、プレレクチャーは幕を閉じました。
■感想シェア会
プレレクチャー終了後、ユースプログラム参加者たちが集合。今の体調が"元気"、"疲れている" 、"頭がスッキリしている"、"ぼーっとしている"の4グループに分かれ、感想やゲストの二人への質問などを話し合いました。以下、質問と回答をまとめました。
中村さんQ&A
Q.誰でも受け入れるオープンな施設の中で、秩序や弊害など気を付けていることはありますか?
A.施設ではないので去る者は追わず、来るものは拒まず、基本的には自由。その人たちの意志が重要。
Q.『じじっか』の活動をどうしてここまで続けられたの?
A.私は自分の名前にミドルネームをつけて『中村・じじっか・路子』として活動している。中村路子個人としてはできなかったと思うし、私も代表としての役を演じているのかもしれない。
菅原さんQ&A
Q.よかったなと思った瞬間は?
A.岡田さんと出会ったから監督になれた。"おかじい"から「監督」と声をかけられたから、監督という役を演じようと思った。
Q.認知症の方に演技をさせることに罪悪感はありますか?
A.人が与えられる役割は重要で、我々は社会生活で役を演じている。ただ、高齢になると役割を奪われていく。"おかじい"は99歳で何者でもなくなってきた。彼はいろんなものを捨ててきたけど、演技だけは捨てない。"おかじい"の演技に対する情熱は今最高潮になっている。演劇という虚構の中にも、目の前の人と何か信じあえる瞬間があれば、それは真実だと思う。
最後に長津さんは「今日のプログラムが作品を観るためのフックになればと思っている。次回は『恋はみずいろ』の鑑賞。"おかじい"をはじめ出演者たちが実際に舞台に上がっている様子を、今日の菅原さん、中村さんの言葉などの記憶をもとに、みなさんがどう演劇を観てくれるかなと思っています」と語り、ユースプログラムは終了しました。
感想 一部抜粋
・最近、祖母に認知症の傾向が見られるようになりました。祖母の世界では、私はまだ幼い子どものままかもしれない。孫として彼女の世界感に全力で付き合うことも一つの在り方かもしれないと感じました。
・ワークショップの構成が素晴らしかった。「老いを演じるってなんだろう?」という不安が一気になくなりました。『恋はみずいろ』の鑑賞が更に楽しみになりました。
・介護する人とされる人の関係は対等性を保つのが難しいと思った。嘘をつくのは、優しさゆえの演技もあると気づき、コミュニケーションを俯瞰するのが面白いと感じました。
・家族じゃない人との関係があることで。家族と向けあえるようになるのかもしれないと思いました。
・『じじっか』の「サンタの荷物」の理想が非常に印象的だった。相互に抱えているものを相互に受容、尊重し合い障害を取り除いて信頼関係を構築できるような関係がとても魅力的に感じました。